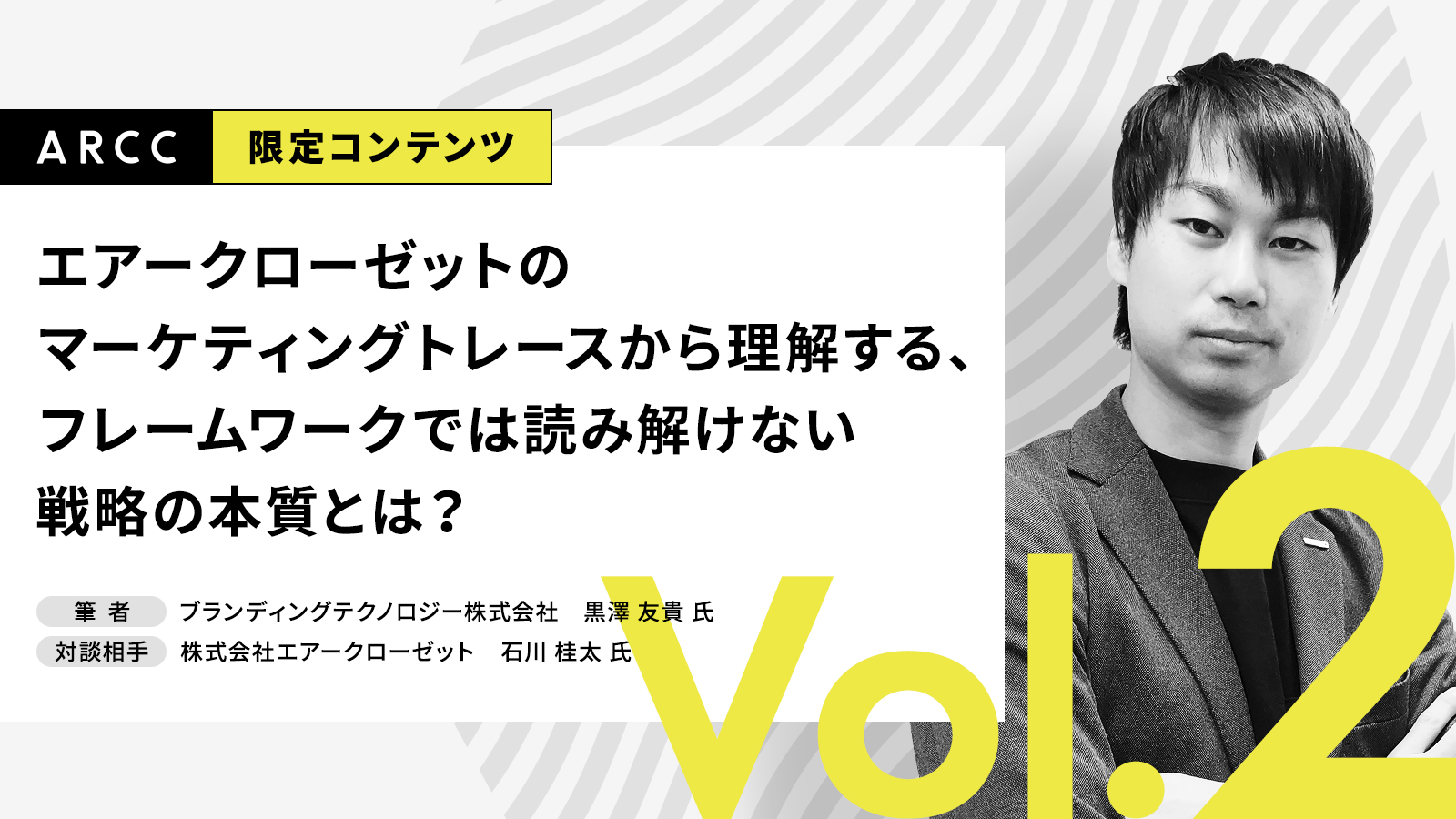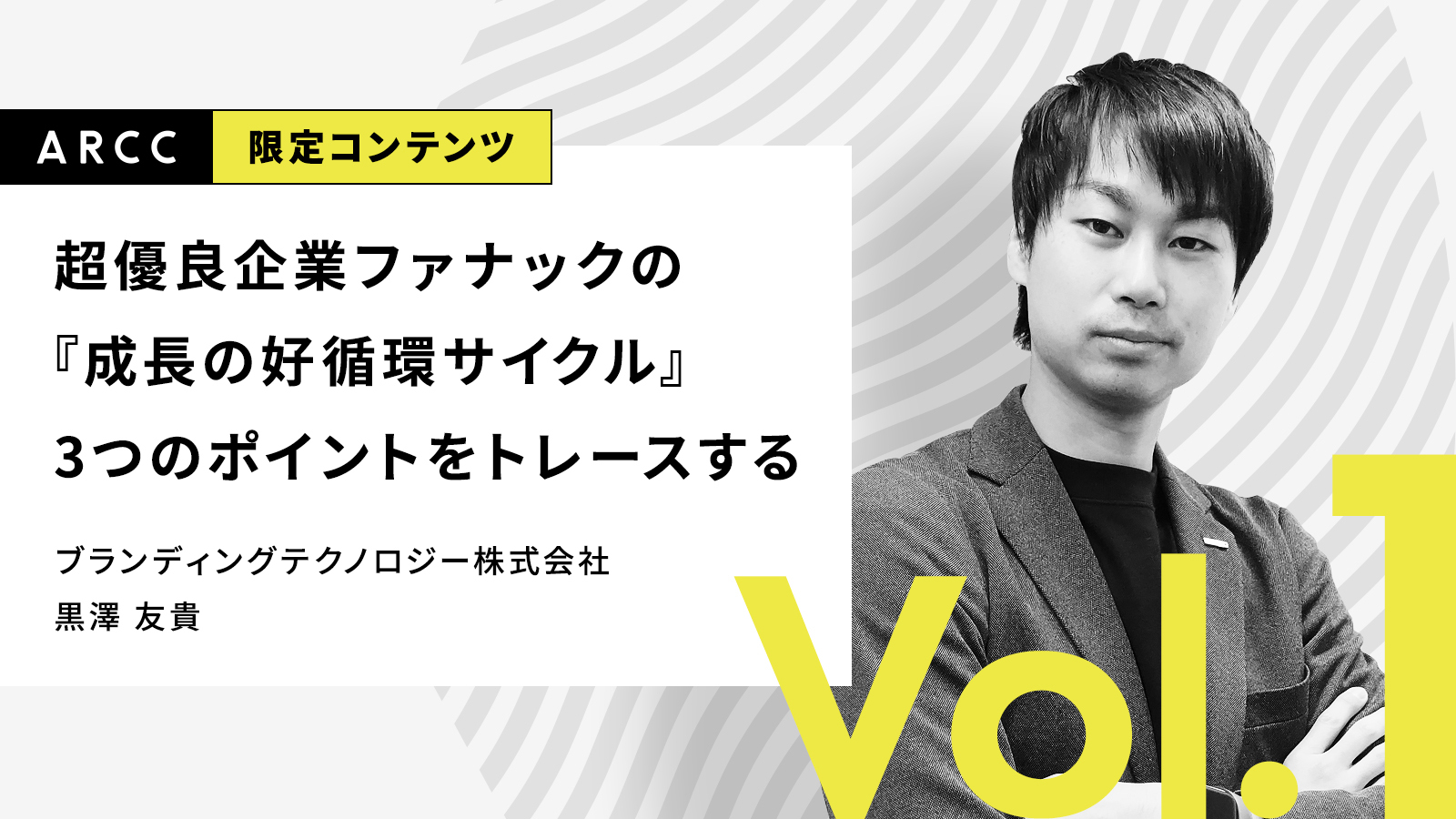前回、営業支援の視点でマーケティングオートメーションの3つのメリットを挙げました。
それはこのような3つでした。
- リード顧客の心理状況を想像できる
- アプローチすべきタイミングを知ることができる
- 実りあるリードジェネレーション
それぞれ詳しくは参考記事を見ていただくとして、この3つを踏まえた上で、今回はもうすこし詳しい事例を参考に、3つのポイントを見ていきましょう。
参考記事:「営業支援の視点で考えるマーケティングオートメーションの3つのメリット」
量から質への転換
マクロな視点で世界を見た時、先進国ではこれから『人口減』という事象が、ほぼ間違いなく起きる予見があります。

人口全体も減少していきますが、当然ながら労働人口も減っていきます。
この不可避な現象を前にして、営業及びマーケティングに従事する私たちは、何を考えなくてはならないでしょうか?
一つは、量から質への転換です。
顧客に対して『量』を念頭に営業・マーケティングアプローチを展開しても、従事する人の数が多ければ、それだけ成約につながる可能性が高いと言えます。
一方で、事業者の人数が少ない場合は、量を追求しても成約にこぎつける可能性は低く、重要なのは『質』です。
その状況を解決していくための一つの解としては、テクノロジーの進化を活用して、人を増やすのではなく、テクノロジーで代替していくといったものがあります。
MAツール「マルケト」を導入した株式会社ユーザベースの事例では、このような言葉が出てきます。
「当初のインサイドセールスチームのKPIはとにかく量を追うというもの。前年の約6倍のアポイント獲得を目標に掲げ、達成したところで、”量から質”への転換が求められていました」
もう少し詳しくみてみましょう。
追わない商談の明確化
経営判断にも通じる部分がありますが、マーケティングオートメーションを活用する上で、何をするかを決めるよりも、「しないことを決める」ことはとても重要です。

株式会社ユーザベースの事例では、同社のサービス「FORCAS」のセールスを担う田口 槙吾氏が、追わない商談を決めたことで起きた変化について、このように述べています。
「以前は『脈がない』『時期尚早』と判断される新規案件についても、マンパワーで追っていたのが、Marketo導入によって、マーケティングチームに預けられるようになった。より確度の高い案件に集中し、クロージング作業に注力できるようになりました」
これはまさに、量から質への転換だと言えるのではないでしょうか?
人数を増やすことなく、テクノロジーを活用して成約率を上げることで、質の追求を実現しています。
データの連携
最後は今までの文脈とずれますが、大事なことなので「連携」について焦点を当てます。
ここまで読んだ人の中には、(MAツールを導入してみたいけど、今まで使っていたツールとの連携はできるの?)といった疑問を持った方もいると思います。
3つのメリットでも書きましたが、結論から言うと連携できるツール同士はあります。
むしろMAツールだけを使うよりも、それまで使っていた営業支援ツールと連携することで、さらに活用シーンを発展させることができます。
具体的な事例を見てみましょう。これは、日商エレクトロニクス株式会社の事例からピックアップした言葉です。
Salesforceを見ながら、すぐにアプローチすべき顧客など、ACTIVE基準を3種類に定義。さらに外部の企業情報データやMarketoにおける個人の行動履歴もSalesforceで確認しつつ、コール、メール、リサイクルを判断し、フォロー時の確認事項や電話でのヒアリング項目も細かく規定。その履歴をSalesforceにしっかり残す。
この言葉の前段では、マルケトを活用してリード顧客をインサイドセールスに渡すまでのプロセスが書かれています。
すごく簡略化すると、 ステップメールを通じて顧客の温度感を上げる部分をMAツール「マルケト」で評価して、その後インサイドセールスに渡し、マルケトのデータを含む包括的なデータを営業支援ツール「Salesforce」で観察してアプローチするといった具合です。
このように双方のデータを連携させることで、コンテンツによるマーケティング(温度感を上げる)と、インサイドセールスへの引き渡し、そして電話をかけるタイミングまで計ることができます。
ここまで読んだ方だったら、「営業支援とマーケティング支援」といったように、双方は切り分けることではないとわかりますね。
以上、営業支援に活きるといったテーマでお送りした「マーケティングオートメーション事例3つのポイント」でした。

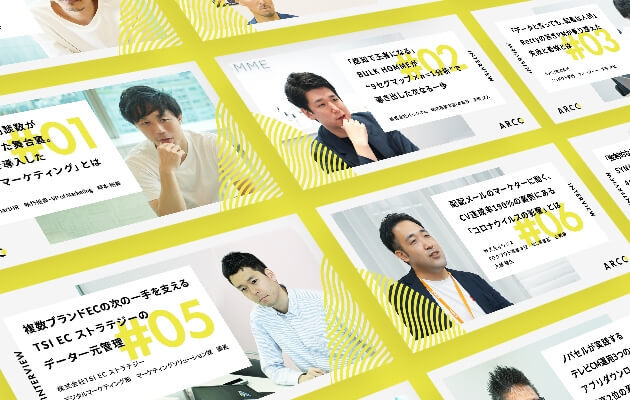
ARCC限定イベントへのご招待・限定コンテンツの配信・
新着記事の案内・イベント情報の先行配信など、特典が満載です。